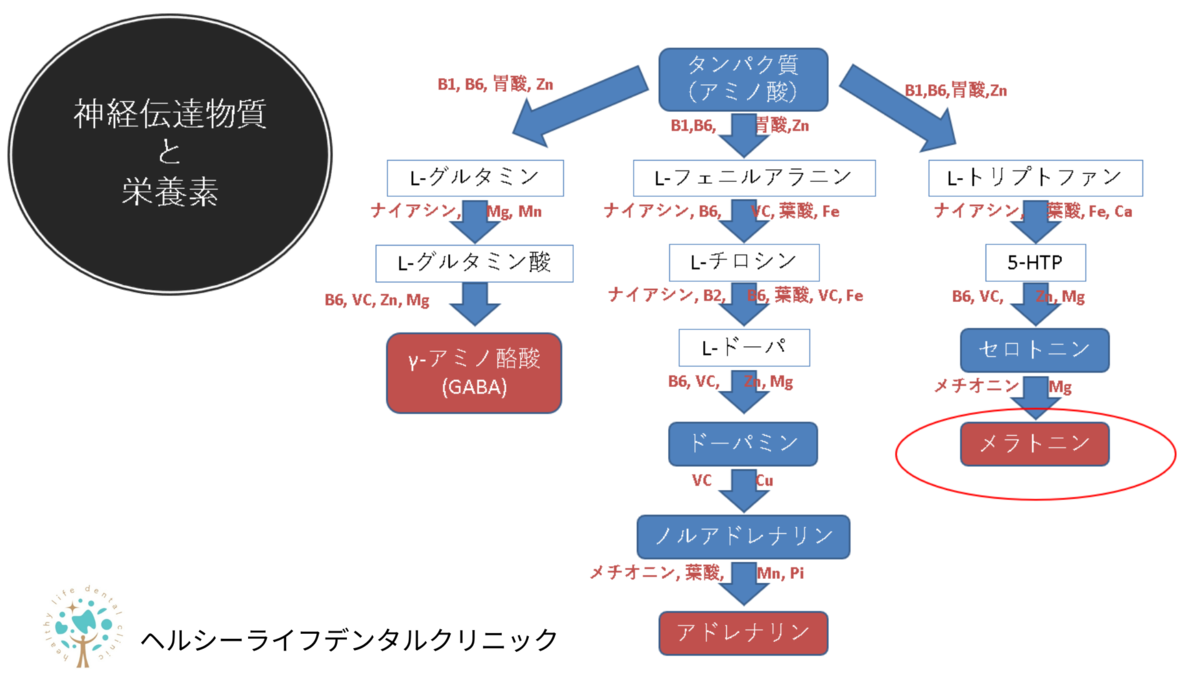どうも、歯科医師・歯学博士の手塚充樹です。今回はビタミンDとお口の筋力の関係について大変興味深った研究を紹介します!
体の方の筋力との関連や、アレルギー、風邪など何かと話題が上がることが多いビタミンDですが、お口の中の状態とも密接に関わっています。

高齢者のビタミンD不足と口腔の筋力:義歯の安定性との関連性
高齢になると、体全体の筋力が衰えるだけでなく、口元の筋力低下も問題となります。特に、この口元の筋力は義歯(別名、入れ歯)の安定性にも関係していると言われています。
研究の方法
38歳から75歳までの完全無歯顎患者130人が調査対象となったそうです。その調査の目的は、ビタミンDのレベルがこれらの患者の健康状態にどのような影響を及ぼすかを理解することだったとのこと。
この研究で選ばれた130人は、男性71.5%、女性28.5%、平均年齢60.62±6.94歳の患者だったそうです。研究の焦点は、ビタミンDの状態(S Vit D)と筋肉の厚さおよび活動性との関係を示すことです。
この研究の中で用いられているような、咬むための筋肉の筋力を測れる筋電図は当院でも測定できます。
筋電図測定は、顎関節症などの病名がつけば保険診療で測定が可能です。
筋電図測定が有効なパターン
1.顎関節症がつらい
2.かみしめ癖がある
3.かぶせ物が壊れたり詰め物が外れやすい
4.口の機能が落ちてきていて、咬んでいると疲れる
こちらの咬筋の筋電図測定検査については、咬む力が強すぎる場合、もしくは弱すぎる場合に応じてそれぞれ対応方法があります。
今回の論文のように義歯を入れた方の機能を測るという意味でも有効ですね。
その他の研究にあたっての対象の選出条件
参加した方々全員が、顎関節症診断基準(DC/TMD)に基づき顎関節症の評価を受けたとあります。これは、病状の評価を正確に行い、調査対象として適切な人物を選ぶための基準となったそうです。
具体的な適格条件としては、症状がなく、無歯顎状態が1年以内で、顎関節症の診断から1年以内の方々が対象だったとのこと。また、歯槽骨隆起が高く新義歯を装用している方々も対象となったそうです。
また、全身疾患のある方々、薬物アレルギーのある方々、免疫薬物療法を受けている方々、虚弱体質で筋力が低下している可能性のある方々、筋ジストロフィーの可能性がある方々、外傷や歯周病で歯を失った方々などは、調査から除外されたとされています。
要するに、調査の結果に影響を及ぼすと考えられる病気を持っている方は研究対象から除外したということですね!
選ばれた全ての患者がビタミンDレベルの評価を受け、その結果に基づいて分類されたとあります。ビタミンDが十分な患者は対照群とされ、ビタミンDが不足している患者は治療群とされたそうです。
この研究は、ビタミンDの役割について深く理解するための新たな道を開くもので、特に全身の健康状態と口腔の健康状態の間の関連性に焦点を当てているとされています。
まさに全身と口腔のつながりですね。
研究結果
研究結果のまとめです。
1.ビタミンDの服用により、血中ビタミンDの平均値は有意な増加がみられた。
2.ビタミンDの服用から3ヵ月後と6ヵ月後には、重度の血中ビタミンD不足患者は認められず、血中ビタミンD不足の患者数は大幅に減少した。
3.血中ビタミンDレベルと筋肉の厚さおよび活動量との間には、時点によってさまざまな相関関係が認められた。
男性と女性では、レベル0とレベル6でS Vit Dの平均値が異なっていた。レベル0では統計的に有意な差が認められたが、レベル6では有意な差は認められなかった。
4.研究スタート時点においては、患者の職業がビタミンD値に有意な影響を与えた。
5.比較を行ったところ、3つの変数(血中ビタミンD、筋厚、筋活動)のすべてのレベルで有意差が観察された。
6.ビタミンD欠乏患者にビタミンDサプリメントを投与したところ、筋活動に改善がみられ、義歯の保持力にも改善が認められた。
結論
これらの知見は、ビタミンD欠乏患者におけるビタミンDサプリメントの潜在的な利点と、筋肉の健康と義歯の保持への影響を強調するものである。
食生活とビタミンDの重要性
咀嚼力(食べ物を噛む力)が弱まると、食事内容に制約が出てきます。糖質、脂質、タンパク質といったエネルギー源主体の食生活が増え、微量栄養素(ビタミンやミネラルなど)が次第に不足してしまいます。これにより、細胞の働きに支障が生じ、徐々に老化や代謝障害による病気が現れる可能性があります。また、健康意識や活力の低下にもつながる可能性があります。
ビタミンD不足は誰にでも起こり得る
先日引用した研究によれば、ビタミンD不足という問題は、年齢や性別、好きな食べ物に関わらず、誰にでも起こり得ることが明らかになりました。しかし、職業や日照時間、住んでいる場所(都会か田舎か)などは、ビタミンDの濃度に影響を及ぼすとのことです。
ビタミンD不足の現状とその対策
一方で、心配なことに、この研究によれば、ビタミンDが十分に摂れている人はわずか2.3%しかいなかったという結果が出ています。この問題は、時に「栄養パンデミック」とも表現されます。しかし、希望を持つべきデータもあります。ビタミンD補給療法を3ヶ月行った結果、大多数の人(正確には62.3%)が十分なビタミンDを体内に確保できるようになったという報告があります。
ビタミンD摂取による筋力改善
さらに、ビタミンD摂取により、咀嚼に必要な筋肉、いわゆる咀嚼筋(特に顎周辺の筋肉)の厚みと活動が改善されたとの結果が示されました。つまり、ビタミンDの摂取だけで筋トレの効果が得られるということです。
食事のバリエーションと全身の筋力
咬む力が回復すると、食べられる食材のバリエーションも増えるでしょう。そして、ビタミンDが全身の筋肉量を維持する助けになるとすれば、筋肉量の減少に伴う体の虚弱状態(サルコペニアなど)の改善や運動機能の向上も期待できます。
ビタミンD療法の推奨
ビタミンD欠乏症がいかに広く、どれほど深刻な影響を及ぼしているかを考慮すると、研究者たちは歯のない高齢者の栄養介入としてビタミンD療法を強く推奨しています。
ビタミンDの不足はどうやって調べる?
ビタミンDはビタミンの中でも唯一、血液検査で過不足がわかりやすいビタミンです。
血液検査をおこなえばすぐに血中濃度で判断ができますよ。当院でも測定ができますのでご希望があればお気軽にお問い合わせください。
食材では摂りきれないものにも焦点を当てて健康で長く過ごすサポート
患者さんに対しては、何を食べるべきかだけでなく、ビタミンDについても考慮することが大切です。私たちは来院された方々の健康状態の向上をサポートしたいと考えています。
引用元
- PMCID: PMC9961876
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
院長 手塚 充樹 歯科医師 歯学博士(口腔内科学専攻)
口の中のデータを全身の観点で解釈する専門家・探求家。 口腔内科学や歯周医学や分子整合栄養医学などの観点から、再発を抑える精密な歯科治療を推奨している。 診療分野は、口腔外科領域の治療、歯周組織再生療法、歯周外科、インプラント、ダイレクトボンディング、セラミック治療、根管治療など幅広く対応している。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ヘルシーライフデンタルクリニック 〒105-0004 東京都港区新橋1-17-2ダイワロイネットホテル新橋B1F 「口から未来を明るく、美しく」